
一之瀬 隼(いちのせ・しゅん) 自動車部品メーカーの現役エンジニアとして、CASE関連の製品開発を担当。2020年春より、製造業関連のライターとして活動。
>>執筆者サイト
SDVが変える車両開発とビジネスモデル:自動車業界よもやま話
2025年07月29日
コラム

前回の記事では、SDVの概要やSDVが消費者や自動車業界に与える大きなインパクトについて解説しました。今回は、SDVによって車両開発プロセスやビジネスモデルがどのように変化するか、考察していきます。
SDVによる車両開発プロセスの変化
前回の記事でも紹介したように、自動車の開発プロセスはSDVによってハードウェア主導の開発から、ソフトウェア主導の継続的な開発へと移り変わっています。ここからは、具体的な変化点について紹介します。
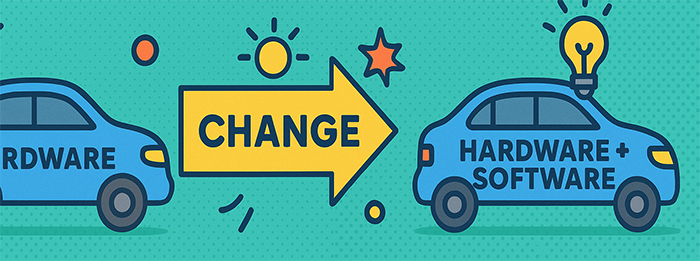
ウォーターフォールからアジャイルへ
一般的に自動車関連のソフトウェア開発は、要件定義→設計→実装→テストのように一連の流れで開発を進めていくウォーターフォール開発で行われています。しかし、近年参入が続いているIT企業やEVを中心に扱うメーカーでは、短期間の開発サイクルを繰り返すアジャイル開発が主流です。
SDVの価値を高める方法の1つとして、消費者が車両を購入した後に、新たな機能を高頻度で追加することが挙げられます。高頻度での機能追加を実現するためには、アジャイル開発は効果的な開発手法です。アジャイル開発に取り組む企業も増えています。
一方で、従来から自動車業界で製品開発・部品供給を行っているメーカーでは、ソフトウェア開発のプロセスを変えることは簡単にはできません。自社の扱う製品や機能の開発に対して、本当にアジャイル開発が望ましいのかという検証が必要です。検証や開発手法を変更するための準備には時間が必要なため、アジャイル開発が一般的になるまでには時間がかかるでしょう。
専用ECUから統合ECUへ
従来、自動車に搭載されているECUはエンジンやステアリング、ブレーキなど製品ごとに分かれていました。しかし、SDV/OTAでソフトウェアアップデートを行う場合、ECUが分かれていると、それぞれのECUに対して個別にアップデート作業を行う必要があるため、時間がかかります。そこで、近年は複数の製品を制御する機能を集約した統合ECUの開発が進められています。
統合ECUはアップデート対象のECUを減らすことができ、管理が容易です。また、接続する配線を簡素化することで設計工数や車両重量、コストの最適化に繋がります。統合ECUの採用はSDV以外にもメリットがあるため、今後は統合ECUの採用が増えていくと考えられます。
SDVによるビジネスモデルの変化
前回の記事でも紹介したように、自動車におけるビジネスモデルとしては車両の販売と、定期点検・整備などのメンテナンスが一般的でした。しかし、SDVの登場によって自動車業界でも新たなビジネスモデルが生まれています。
サブスクリプションによる機能アンロック
SDVによって、車両開発時には機能に対応できるハードウェア及びソフトウェアを搭載しておき、サブスクリプションサービスに登録している期間のみ機能を使用できるようにすることが可能です。オプション選択されるような機能、特定の期間のみ必要とされるような機能がサブスクリプションの対象となり、消費者は対象機能を必要とする期間のみ課金することで利用できます。また、従来は対象機能ごとにハードウェアやソフトウェアを分けて開発していましたが、あらかじめすべてに対応可能な共通のハードウェア・ソフトウェアを開発することで全体の開発コストを低減できます。消費者は必要な機能だけを選択することでコストを抑えつつ、魅力的な機能を利用できるでしょう。
継続的な開発による機能ごとの販売
OTAで遠隔でのソフトウェアアップデートが可能になることで、継続的に開発した機能を単体で販売することが可能です。日本国内でも、既に販売後の車両をアップデートすることで運転時の快適性を向上させるような機能が販売されています。今後は、利便性・快適性を向上させるような機能、消費者の好みにカスタマイズできるような機能の開発・販売が増えていくでしょう。
ビジネスモデルの変化に注目
今回は、SDVによって変化する車両開発プロセス、ビジネスモデルについて紹介しました。北米や中国の新興自動車メーカーを中心に、SDVと共にさまざまな変化が生じています。国内自動車メーカーでも変化が起き始めていますので、今後は目に見えて増えていくのではないでしょうか。
プロフィール
